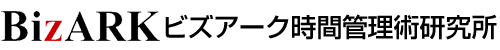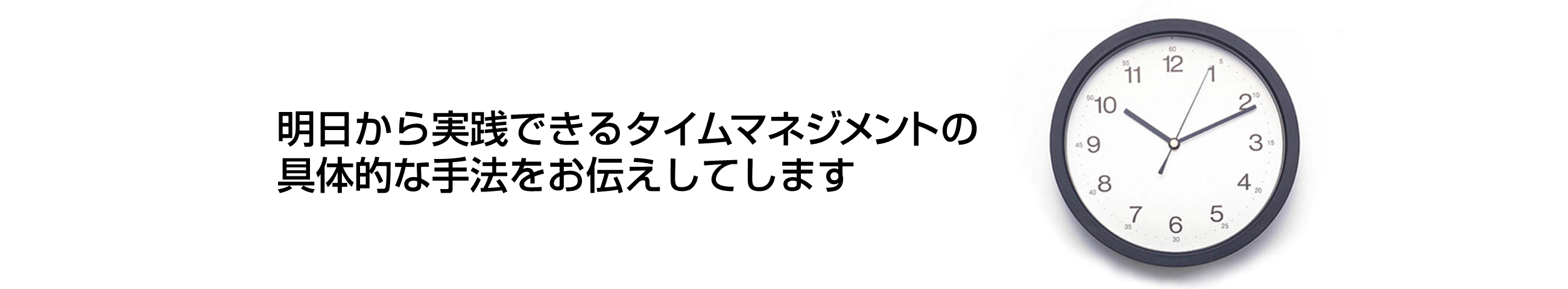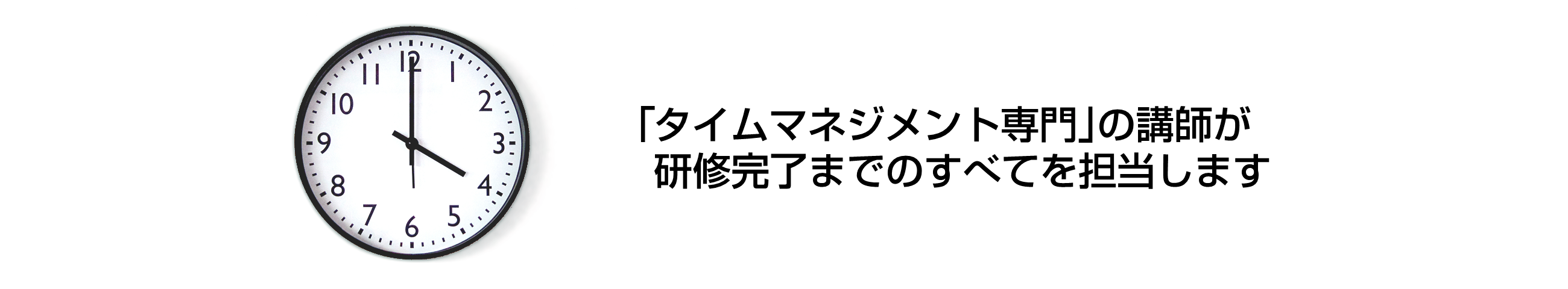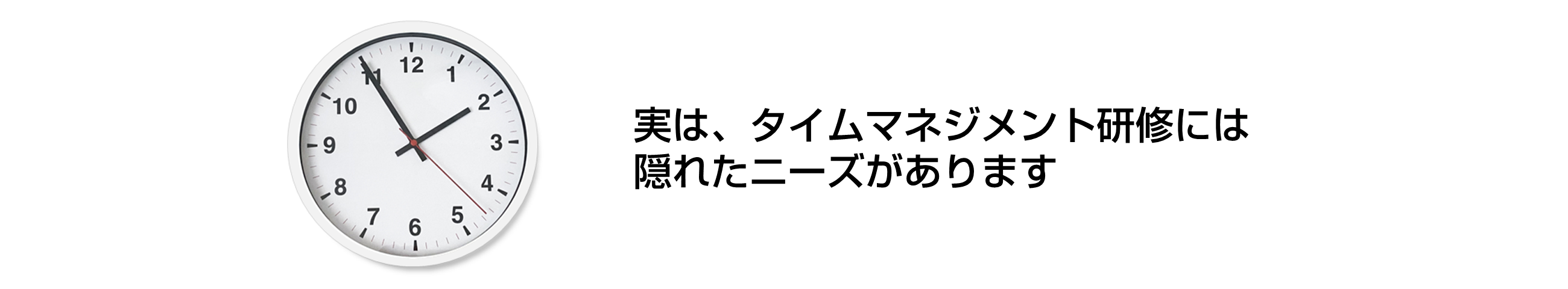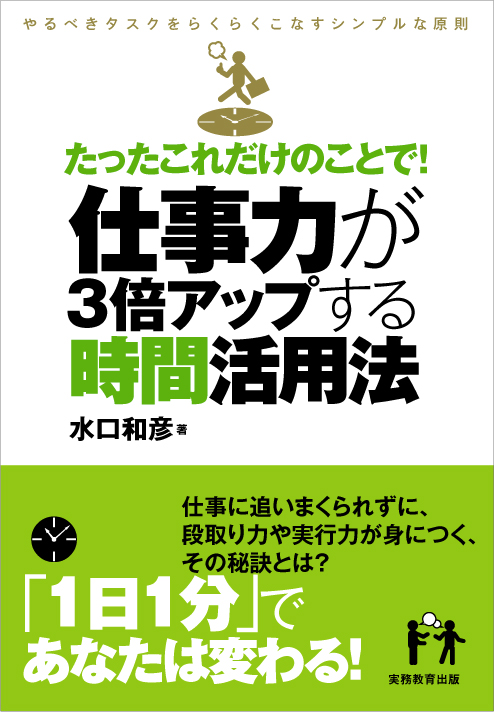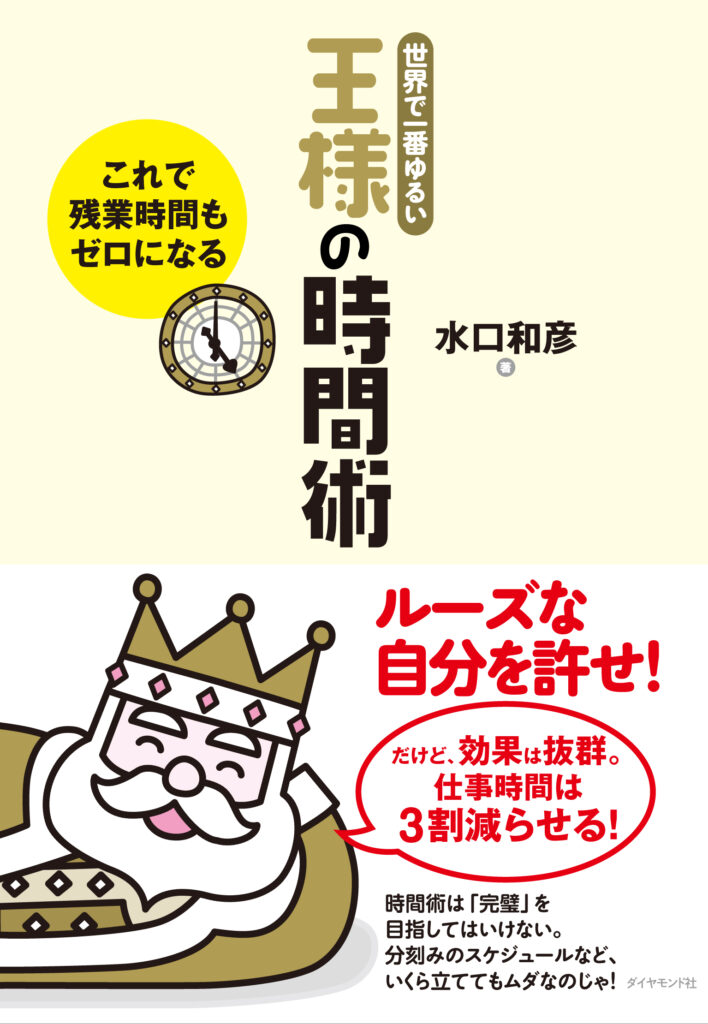タイムマネジメント(時間管理)を専門に、研修・講演・執筆を行っています
代表の水口です。弊社はタイムマネジメント(時間管理)を専門として講演や研修を行うとともに、教材の制作や監修、書籍の執筆などを行っています。
始まりは2005年の8月のことです。私がインターネットの片隅でひっそりと公開し始めた新しいタイムマネジメントのノウハウがクチコミで評判となり、執筆や講演、取材などのご依頼を頂くようになりました。その後、これを専業とするために独立し、現在までに10冊の本を執筆し、1000回以上の講演や研修を行っております。また、通信教育(2社)やeラーニングを提供している会社(1社)、社員教育用DVDを制作している会社(1社)から依頼を受け、教材の製作を行ってきました。早稲田大学の社会人講座も担当しております。
(講師プロフィールページもご覧ください)
なぜ、このタイムマネジメントの方法がこれほど評判になったのでしょうか? その理由のひとつは、これまでに時間管理について言われていたことは「使えないノウハウ」だったからではないでしょうか。
例えば、タイムマネジメント・時間管理としてよく言われる手法に「仕事に優先順位をつけなさい」というものがあります。仕事にA・B・Cと優先順位をつけ、優先順位の高いものから順番にやっていけばいいという考え方です。
この考え方は、実際に実践してみると様々な問題が起こります。その問題点の1つは、仕事があふれてくると優先順位の低いものを先送りせざるを得ないことです。月曜日にやり残した仕事を火曜日に、そしてまたやり残した仕事を水曜日へと先送りすることになってしまいます。
一方、仕事の中では「優先順位が低いからできませんでした」という言い訳が通用するでしょうか? 通用しないことの方が多いですよね。優先順位がどうであれ、一度「やる」と引き受けたことは放り出すわけにはいかないものです。
「優先順位」のやり方を信じて仕事を先送りしてしまうと、仕事の期限が迫ってきた頃に、ようやく自分ではやり遂げられないことに気付きます。しかも、その時には(時間が経過してしまっているので)「今さら人には頼めない」という状況になっています。結局「自分でやるしかない」と、遅くまで残業してなんとか終わらせるしかありません。仕事量の平準化や「働き方改革」には程遠い状況ですね。
このように、「優先順位を付ければいい」という考え方は「出来ない仕事を先送りしてごまかすこと」につながりやすいのです。先手を打って行動することが出来ず、後手に回りやすいやり方とも言えます。仕事量が少ないうちはそれほど問題はありませんが、仕事量が多くなると必ず破綻しますし、もちろんストレスもたまります。
実はこれ、私自身が過去に経験したことなのです。
うまくいくタイムマネジメント、うまくいかないタイムマネジメント
私は前職でのエンジニアの仕事が多忙だった時期に、手帳を使ったタイムマネジメントを試みました。毎日仕事をリストアップして優先順位を決め、やり残した仕事は翌日のページに転記して、また優先順位をつけて、ということをくり返していました。
毎日毎日、その日のリストをクリアすることを目標にしていました。それにより「うっかり仕事を忘れてしまう」というトラブルは無くなりました。しかし、仕事の効率はそれほど上がりませんし、仕事上のストレスは減るどころか、逆に増えてしまいました。
その日の仕事をリストアップし、そのリストをクリアすることを基本にしたやり方は、常に不安がつきまといます。やり残した仕事は翌日に持ち越しますから、明日はまだしも、明後日やその先の状況は予想できませんし、来週どうなっているかなんて、全く予想出来ないのです。
先が見えない中で仕事をするのは、非常に強いストレスを感じます。例えるなら、真っ暗な中、懐中電灯で自分の足元だけを照らしながら歩いているようなものです。明日、明後日にも自分の仕事が破綻しないかという不安が常につきまといました。実際に、手帳の明日のページを開くのが怖い、と思ったことが何度もありました。先が見えないので「とにかくできるだけのことをやっておこう」と、毎日遅くまで残業していました。
私は最初、こういった不安やストレスは、仕事が忙しいためだと考えていました。しかし、これらはその仕事本来のストレスではありませんでした。仕事そのものではなく、タイムマネジメントのやり方に問題があったのです。
効率を上げ、ストレスを減らせたタイムマネジメント
それがわかったのは、タイムマネジメントのやり方を試行錯誤し「これならうまくいく」という方法が見つかってからです。詳しい方法は別途ご紹介するとして、大まかな特徴はこんな感じです・・・。
・タスクの実行順序を優先順位から考えるのではなく「実行するタイミング」の方を重視する。
(タスクを記入する場所や記入の仕方を変える)
・「タスクに使える時間がどれだけあるか」を素早く判断できるようにする。
(時間が足りなくなりそうな場合に早い段階で気づけるようにする)
・「突発の仕事が飛び込んでくる」ことを想定して計画を立てる。
突発の仕事が飛び込んできたときの判断基準を具体的に決めておく。
・できるだけ手間をかけずに「時間の使い方」を記録し、実績をふり返ることで次への改善につなげる。
こういった方法により、タイムマネジメントは大きく変わります。自分の仕事の見通しがよくなり、仕事量を平準化しやすくなり、行動の無駄がなくなり生産性・仕事の効率が高まりました。実際、月に100時間以上していた残業が、月に30時間以内に収まるようになりました。私自身、タイムマネジメントのやり方しだいでこんなに違うものかと驚きました。
もうひとつ驚いたのが、仕事上のストレスが大きく減ったことでした。先の見通しがよくなり、不安なく仕事を進められることや、期限ギリギリに慌てなくてもすむようになったこと。そういった効果で、こんなにストレスが減るものかと驚きました。もちろんワーク・ライフ・バランスも大きく改善しました。
そして、私がこのノウハウを公開し始めたのは、この知恵、経験を広く伝えることが私の使命のように思えたからです(ちょっと大げさですが)。それが好評を頂いたので、タイムマネジメントの手法を伝えることを専業にしようと独立したのが2006年のこと。そして現在もいろいろな組織でタイムマネジメントの研修を行っています。
では、私の話はこのくらいにして、タイムマネジメント(時間管理)の研修について紹介していきましょう。
タイムマネジメント講演・研修についてのQ&A
タイムマネジメント(時間管理)の講演や研修について、よく頂くご質問と回答を紹介します。
お気軽にお問い合わせください
研修や講演、取材などのご依頼や
ご相談、ご質問などございましたら
お気軽にご連絡ください。
(クリックするとお問い合わせ用ページが開きます)
メールマガジンを発行しています
講師のメールマガジンを発行しておりますので
よろしければご登録ください
いつでもご自由に登録・解除して頂けるように
メルマガ発行スタンド「まぐまぐ!」を使用しております